| 1 |
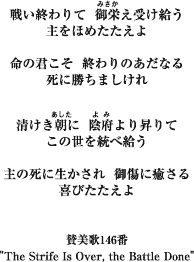 |
| 最後の日 |
飛空挺から見下ろす地上は一面の緑に覆われている。 光り輝くライフストリームが、あの禍々しく大地を震撼させ続けた巨大なメテオを包み込み、まるでその力を取り込もうというように消滅させた後、優しい緑色の軌跡を僅かに残して地中へ戻っていった。 静まり返った地表は風が強いのか、木々や草をそよがせてはいるが、衝突間近の小惑星が巻き起こしていた磁場の変化や地震は治まったように見える。 クラウドはガラス窓に額を押し付けて、外の様子を見つめていた。 「終わったの、か?」 巨体を震わせて言ったバレットの言葉に、硬直させていた乗組員全員の身がはっと揺らいだ。 「やった…の? メテオ、消えたよ…」 「生きてる。あたしたち助かったんだ」 手を握り、座り込んだティファとユフィが泣き出した。 それをきっかけに互いに抱き締め合い、喜び合う歓声にブリッジはひと時騒然となった。 最もメテオの被害を受けたミッドガルは、倒壊した神羅ビルのあちこちから炎を吹き上げ、上層プレートに並ぶ建物も所々火災を発生させているようだった。ミッドガルの人々は殆どが街の外やダウンタウンに逃れたはずだったが、この様子ではまったく被害がないとは思えない。 それでもこの船の中は喜びに溢れていた。 長い戦いの果てに辿り着いた結果だ。 「クラウド! どうしたのよ、わたし達やったのよ!」 ガラスに張り付いていたクラウドの肩を、駆け寄ってきたティファが抱き締めた。 「ティファ…」 「メテオは、消えたのよ。わたし達の星は無事なのよ、クラウド!」 まだ呆然としているクラウドを掴んで揺さぶる彼女は、黒い大きな瞳に涙を滲ませ、満面の笑みだ。 ずっと守りたかった彼女をやっと笑顔にすることが出来たと、クラウドもつられて微笑を浮かべた。 「ああ、ティファ」 「長い道のりだったな。やっと正しい出発駅を発車できるってとこかもしれねえが」 バレットにも肩を叩かれた。 「でも、実は本当にセフィロスを倒せるなんて自信は、これっぽっちもなかったんだけどよ」 バレットのいい様に皆が声を上げて笑う。 クラウドも笑おうとした。 だがそれは叶わなかった。 手に入れたものより、クラウドの中から抜け落ちたそれは、意識的に無視するには強大だった。いや、失ったそれこそがクラウドの全てだったのだから。 「…クラウド?」 込み上げたものを押し殺すように俯いたクラウドの顔を、足元まで歩いてきたナナキは見上げる。獣の姿の彼に表情があるならば、酷く不安そうな顔だった。 「どうしたの、クラウド」 心配そうにウロウロとする彼の頭に手をやり、柔らかい毛並みを撫でる。 暖かく、太陽の匂いがする彼のそこに、クラウドは腰を屈めて顔を埋めた。 「セフィロス…オレが、殺した」 言葉にしたと同時に足が萎えた。 「オレが、殺した。この手で」 冷たい鉄板の床に膝を突き、両手で顔を覆う。 血の匂いがする掌。 彼の返り血を受けた頬に触れる。 向き合いたくなかった事実が、今頃になってクラウドに圧し掛かった。 「ああ、あああ…」 掌の血は乾いてこびりついていた。服に擦りつけて拭っても、黒く変色したそれは落ちそうもない。 「セフィロス…セフィロス。オレが…」 必死で血を拭おうとするクラウドの腕を、ヴィンセントが掴んで止めた。 「ヴィンセント…セフィロスは死んでないよな? きっと生きてるよな?」 目線の高さに持ち上げた掌の向こうに、ヴィンセントが何かに耐えるように唇を噛み締めている。 クラウドは不思議に思った。 彼が自分の腕を掴んでいるというのに、なぜこんなに掲げた手が震えるのだろうか。 どうしてこれほど彼の顔が水中にいるように歪むのだろうか。 「クラウド、お前だけじゃない。お前のせいじゃない」 ヴィンセントの宥める声にも、クラウドの震えは止まらなかった。 「一体…どうしたの。何を言っているの、クラウド」 ヴィンセントの後ろに不審げに眉を顰めたティファがしゃがみこんだ。 「セフィロスは、もう倒したのよ。もう何も心配はないのよ、クラウド」 「よせ、ティファ!」 ヴィンセントの制止に言葉を止めたティファは、クラウドを見る目を見開いた。 「嘘だ…あの人が、オレを置いて逝くはずない。そんなはずない」 ヴィンセントに腕を預けたまま頭(かぶり)を振るクラウドを、彼は静かに見つめたままだ。 「違う。違うと言ってくれ、ヴィンセント!」 だが静かに、ヴィンセントは首を横に振った。 「クラウド、セフィロスは…死んだんだ。俺たちの手で倒したんだ」 |
* * * |
「私、何か勘違いしてたみたい」 ティファは独り言のように呟き、こちらを見たナナキとバレットに顔を向けた。 笑おうとしても頬は強張って、とても出来そうになかった。 「なんのことだよ」 「クラウドにとって、本当に大切だったものって…なんだったのかしら」 「オイラたちはクラウドの本心を知らないまま戦ってたのかなあ…」 当の本人は先程酷く錯乱して暴れ、無理矢理押さえつけたヴィンセントが部屋へ連れていった。 暫くして静かになったが、これまで淡々と最後の戦いに臨んでいた彼の錯乱振りに恐怖して、誰もが室内の様子を伺うことを恐れている。 ティファ自身もそうだ。 ここに集まっている皆がセフィロスを憎んでいた。自分たちの住む星を壊そうという悪人だという以上に、それぞれが彼に個人的な恨みを持っていた。 ティファは父を殺された。それまでティファを慈しんでくれた村の人々も彼の狂乱の犠牲になった。 そしてここにいる全員に希望を与えてくれたエアリスも。 中でも最もセフィロスに恨みが深く、誰よりもセフィロスと決着をつけたがっていたのはクラウドだったはずだ。誰よりも、あの死神の滅亡を喜んでいいはずだ。 それが、先刻取り乱したクラウドの言い分は―――。 「様子…見てくる」 座っていたポールから腰を上げたティファを全員が見上げたが、止めもしない。きっとティファと同じ混乱を、彼らも感じているのだろう。真実は気になるがそれを聞いてはいけないようにも思う。 ティファはエンジンの振動を受ける通路を歩き仮眠室に向かった。 通路を出てすぐ脇にあるその扉は、全てを拒絶するようにぴっちりと閉じられている。室内は静かなまま。ティファは自動扉の開閉ボタンを押し、横にスライドしたそこに足を踏み入れた。 仮眠室は小さな二段ベッドが三つあるだけの狭い空間である。 その一つの下の段に彼は横たわり、その前の床にヴィンセントが座りこんでいた。ヴィンセントはティファの気配に顔を上げた。 「今は…落ち着いている」 ティファはヴィンセントの肩越しに、クラウドを見下ろして息を飲んだ。 薄い枕に頬を当て、ヴィンセントの方を向いているのに、その大きく美しい瞳は何も映していないようだった。まるでミディールのライフストリームから救出された時を彷彿とさせる、生気のない目。 だが一つ違うのは、その目尻から絶え間なく涙が流れていることだった。 時折滴になったそれが頬を通り、枕やシーツに染みを作っている。 「…クラウド」 「ティファ、今は何も言うな。寝かせてやれ」 ヴィンセントに押し留められ、ティファは続きの言葉を飲み込む。 「クラウド、私から皆に話してもいいか?」 ヴィンセントはクラウドにこれ以上ないほど優しく問い掛けた。 だがクラウドは無言で首を横に振る。目は、やはり何も見ていない。ティファさえも。 「じゃあ、後で自分で話すな?」 頷いた。 「分かった。落ち着いたら出て来い」 立ち上がったヴィンセントに促され、ティファも部屋を後にした。 名残惜しげに振り返った視界で扉が閉まった途端、室内から呻くような、悲鳴のような、慟哭が響いた。 一晩中彼の嗚咽は途切れず続いた。 扉の外のティファも、訳も分からず流れ落ちる涙を、止めることが出来なかった。 ティファはクラウドを愛していると思う。 自分のこの気持ちがあったからこそ、魔晄中毒で我を失くした彼を救い出し、本来の彼を取り戻すことができたのは事実だ。 そしてティファの帰る場所は、もう彼の元しか残っていない。故郷を失い、二度目の故郷になった七番街の店ですら今はないのだから。 だが彼女自身が今は自分の気持ちに疑問を感じていた。 ティファが彼に縋る時は、常に消去法で選んだ結果だったようにも思えたからだ。 最初はクラウドが故郷を出た時。次々と村を離れていく幼馴染みたちの中で、彼だけが夢を果たしてもティファのことを忘れずにいてくれると思えた。 それにミッドガルで再会し、七番街がプレートの下に消えたとき。クラウドの旅を共にすることでティファは立ち直った。エアリスを失い、クラウドがティファと同様に帰るところを持たない孤独な存在になった時、彼が共にあるべきは自分だと思った。 しかしティファは彼と喜びを共有したことは、実は一度もなかったのかもしれない。 この星の救済も、多くの人間の敵であったセフィロスの死も、クラウドにとっては自分と同じ喜びでなかったのだとしたら。 翌朝、ブリッジに姿を見せたクラウドからは一切の感情が覗えなかった。 七番街で再会した時の違和感とも違う。発する空気は間違いなく彼自身のものであるのに、彼を彼と認める何か決定的なものが、一晩の内に抜け落ちてしまったようだった。 真っ赤に充血した白目が、瞳の緑色の輝きと相まって、酷く濁って見えた。 元々白い頬は、それでも旅の間に健康的な色に焼けていたというのに、まるで蝋のように血色がない。 死人のようだとティファは思った。 だがこれほど危うい幽玄の美を持った骸があるならば。 あのセフィロスと良く似ている。 彼の姿に絶句するティファの前を通りすぎ、クラウドは窓から下界を見下ろした。 視線をめぐらせていることは分かるが、感情を示すような動きは一切ない。 「クラウド…大丈夫?」 不安そうに歩み寄って見上げるナナキに、クラウドはいつものように毛を撫でて応える。 だが無言だった。慈しむような優しい微笑もそこにはない。 ティファは掛ける言葉を必死で探した。 「クラウド、辛いかもしれないが、皆に話を…」 全員が硬直したまま彼の様子を見つめていたが、ヴィンセントが切り出したことで漸く肩の力が抜ける。 クラウドは相変わらず無表情のまま頷き、覗き込んでいた窓ガラスに背を預けた。 「何から話せばいいんだろう」 今日初めて彼が発した言葉は、思ったよりもしっかりしていた。昨日までの彼なら同時に浮かべただろう、はにかむような笑顔がなくても。 「お前が話したいことだけを、話せばよかろう」 ヴィンセントが静かに応じる。 ああ、とティファは気付いた。 出会った頃のヴィンセントと同じ気配を、クラウドから感じ取ることが出来る。 押しつぶされそうな後悔と、悲しみと、そして贖罪の機会を望む者の姿だ。 「セフィロスのことを話したい」 クラウドは、セフィロスの名を口にした時だけ、微かに笑んだように見えた。 「まだオレたちの知らねえことがあるのか?」 シドが問いながら床に胡座で座った。 「ああ。誰にも話す必要はないことだと思っていた」 「お前さんが楽になるなら、なんでも聞くぜ。オレは」 シドは煙草に火を点けながらそっけなく云う。 「ありがとう、シド」 呟くように云い、クラウドは俯いた。 そして話し始めた彼に全員が注視し、息を殺した。 彼は事実だけを語り、そこに彼自身の感情は殆ど含まれてはいなかったように思えた。 だがその長い彼の話を聞いた後、ティファはもう一度泣いた。 「オレ、この手で愛した人を、大事な人を、一体何人殺したんだろう」 唯一、クラウドの心の内の見える言葉は、冷静に語られていた故にティファの心を締め付けた。そこに苦笑のひとつもあったなら、皆が救われただろうと思うのに。 彼はもう自分たちの元には留まらないだろうと、ティファは確信した。 |
* * * |
クラウドはバレットの横に立ち、なにげなく胸の下辺りを指で辿った。 そこには彼の亡き想い人が付けた傷跡が赤々と存在する。旅の途中どこかの宿で、バレットはその跡を実際目にしたことがあった。 胸と腹の中央を貫き背中へ抜けた傷。寸でのところで命を取り留めた傷。 果たしてそれは運が良かったからか、それとも意図されたものだったのか。 それを撫でる指先と古い傷口を衣服を通して見つめる瞳は、母が子を愛撫をするようなそんな満足げな様子だ。 「これがここにある限り、絶対に忘れられない。消えても…忘れたくない」 彼の告白を聞いていなければ、バレットはその何気ない言葉に込められた思いを汲み取ることは出来なかったに違いない。 彼の中に眠る喜びに満ちた短い日々を掘り起こすその行為は、同時に彼の罪の意識を呼び起こす。それでもそうせずには居れない、その気持ちだけはバレットにも理解できた。バレットにも同様に、愛した者を失った記憶があるからだ。 これまでバレットは、クラウドを豪胆な男だと思っていた。 剣の扱いも、言動も、潔い男だった。封じた記憶を取り戻した後も、躍動感のある行動派の人物であることは変わりなかった。 だが今目の前にいるクラウドは、支えていなければ崩れてしまいそうな危うさを感じる。それなのに彼を取り巻く空気は、他人の支えを拒絶している。 あのセフィロスという強大な男がどんな風にこの青年を愛したのだろうと、バレットは疑問に思った。 バレットには同性を愛したことも、愛されたこともない。大事な友を失ったのはバレットにとって大きな傷にはなったが、クラウドのそれとは比べるべくもない。 愛したが故に相手を滅してしまうような、殺すのであれば己の手で、と決意できるほどに、強く激しい感情を抱いたことは、女性に対してもなかった。 そして、死んだ男のコピーとして肉体を改造された今、クラウドは身も心も、以前よりも強い結びつきを彼に感じている。でなければこれまでずっと一緒に旅して来た仲間と離れ、独り再び旅に出ようなど、言うはずがない。 傷を癒すための旅であればいい。 それなら時折でも自分たちの元に帰ってくるだろう。 だがクラウドは、きっとあの男を捜しに行くのだ。 そうバレットの勘が囁く。 行かせてはならない。 「行くな」 クラウドの腕を掴み、バレットは金色の髪を見下ろした。 仰向くように背の高い自分を見上げる青年は、珊瑚礁の海を思わせる鮮やかな瞳を向け、泣き笑いのような表情になった。 「行かせない」 「放してくれ。…あんたに剣は向けたくない」 「オレとマリンと一緒に住もう。カームにでも家を借りて。コレルに戻ってもいい」 青年は無言で首を横に振った。 それを見て思った。バレットが無理に止めれば、本気で剣を抜くと。 彼に剣を持たせたら、もう誰も彼には勝てない。なにしろあの英雄を倒したのは、クラウドなのだから。 握り潰せそうな手首はバレットの半分ほどしかないのに。肩や胸こそしっかり男の肉付きだが、それでも細身の青年があの大剣を振り回せるのも、やはり呪われた細胞のせいなのか。 「ごめん」 軽々と振り解かれた。 今この場に彼を留めてくれるなら、どんな女でも男でも構わない。たちの悪い娼婦でも極悪非道な盗人でも、果てもなく報われない道へ旅立つ彼の足を止めることが出来るのなら。 「そんなにあの男が好きだったのか。ティファやオレたちを捨てて行くほど…」 クラウドは肩越しに振り返って、再び首を横に振った。 「クラウド…」 「今でも」 本当に微かな笑みを浮かべて言った。 今でも愛しているのだ、と。 そこまで深く強く無限の愛を、一体誰が彼に与えてやれるというのだろうか。 例え多くの者にとって憎悪すべき人物でも、バレットはそれだけ強く大きな人間は一人しか知らなかった。 |
* * * |
| 飛空挺はミッドガル近郊に着陸した。 ロボットの身体こそ飛空挺にあるが、その正体でもあるリーブが、ミッドガル市内の被害者たちへの救援を要請したからだ。 ミッドガルの外まで迎えに出てきた髭面のリーブは、満面の笑みを見せ、それから一行の酷く消沈した様子に眉をひそめた。 「あの後、何かあったのか?」 リーブは笑顔を消して問い掛けた。 クラウドが昨夜酷く錯乱したことは知っていたが、今日になってからリーブは救援作業にかかりきりで、結局その理由を聞くことはできなかったのだ。 一行のリーダーであり、本来であればこの事態を回避させた英雄であるはずのクラウドが、軽く俯けた無表情で、ただの一言も言葉を発していない。 いつもロボットのカメラを通した映像でしかなかったが、元々無口で無愛想なものの、クラウドはこれほど暗く悲しい顔をする男ではなかったはずだ。 「まあ、道々事情は話すからよ」 シドに肩を叩かれ、市街地へ足を向けた一行の最後にクラウドがついてくるのを、リーブは何度も振り返って確認した。 シドは歩速を緩め、一行の一番後ろにいたクラウドの隣に並んだ。 目は伏せがちでずっと物思いにふけっているような彼は、それでも隣に来たシドに気付いて僅かに顎を上げる。少し青ざめた唇は閉じられたままだ。 「リーブに顔出したら、出発する気だったんだろ?」 シドの問いにクラウドは頷く。 右側に垂らした髪が揺れる。 「なあ、こういう事聞かれても困っちまうだろうけどよ、あの男の何が良かったんだ?」 無神経な質問だとは思ったが、シドはあえて訊いた。 ずっと疑問だったそれをはっきりさせなければ、大手を振って送り出せないと思った。そうしてやらなければ、きっと彼はシドたちの前に二度と現れないに違いない。 「じゃあ、シドは…シェラの何が好きなんだ?」 「オレは別にシェラのやろうなんか…」 横目で覗ったクラウドは微笑を浮かべているように見えた。 「なんでえ。お前に喋らせるにはオレも本音を言えってえのか?」 クラウドはまた小さく頷いた。 脅迫する口調で怒鳴られた訳でもないのに、シドは何故か今の彼には逆らえないと思った。以前の彼とは決定的に何かが変わっていた。 無口なのは元々だが、有無言わせず周囲を従わせてしまうような、何か。 「シェラは…相棒みたいなもんだからよ。別に愛とか恋とか、そんなんじゃねえよ」 「でも、大事だろ?」 やはり彼は微かに笑っている。 とても儚い、消えてしまいそうな。 「…ああ。そうかもしれねえ」 ウータイに『ボサツ』という神仏像がある。 古い宗派で今は信者もないが、ウータイ独特の少々滑稽な顔をした像とは違い、ごく人間に近い表現を成されていることで、美術品として語り継がれたものだ。女のように優美な顔立ちでいながら、意思の揺るがない男の表情で人々を見下ろす。 クラウドの表情はそんな風だと、シドは思った。 ボサツは正確にはヒトが神仏に至る以前の姿だ。この世を憂い、未来にヒトを救う救世主になるといわれている。 人々を救う手立ては、単に住み心地のいい『約束の地』へ誘うだけとは限らない。この星そのものが、その上に生活する人々の不要必要を問う結果も、昨夜までは分からなかったのと同様に、世界を統べる存在は常に冷ややかで残酷なのだ。 神と呼ばれた男を殺める力さえ持ったクラウドが、ヒトを救う者となるか否か、判別することはできない。 「シドはこの旅に出るまで、ずっとシェラと一緒にいたんだろ?」 「ああ。オレがどんなに邪険に扱っても、あいつぁ逃げ出しもしなかった」 「…羨ましいな」 シドの視界の端でクラウドは俯き、地面を見つめながら足を運ぶ。 「オレ、子供だった。あいつの心の叫びを聞くことが出来なかったんだ。それで、逃げた」 「そんなん、お前のせいって訳じゃねえだろう」 「ザックスもオレにそう言ったよ。でもあの時それを聞くことが出来るのは、オレだけだったんだ」 クラウドの頬を、また一筋滴が伝う。 昨夜あれだけ泣いてまだ涙が残っているのかと、シドは唇を噛んだ。 「悪ィ。また泣かせちまった…」 クラウドは顔を上げてシドを見つめた。 以前は嫌な思い出しかシドに残さなかった魔晄の色の瞳が、今はあのライフストリームの流れを彷彿とさせる、優しい色だと思えるようになっていた。 「あんたのせいじゃない。なんか…栓が外れたみたいなんだ。みっともない」 そう言われてしまえば、シドはうな垂れるしかない。 これだけ大人数が集まっても、クラウドの支えになってやることが出来ないのは、一行の全員にとって辛い結果だった。 そしてクラウドはそれを責めもしない。ただ大地の力を秘めた瞳で、静かに皆を見つめるだけだ。 支えもなく孤独に人々を傍観し、強大な力を持つもの――それを神と呼びはしなかったか。 |
* * * |
八番街に辿り付いた一行は、とりあえず僅かな荷を下ろし、今後の算段を始めた。 その輪から外れていたユフィは、同様に少し離れたところで、リーブが拠点としているこの建物の、穴の開いた天井を見上げているクラウドに、ゆっくりと近づいていった。 クラウドの昨夜の告白を、ユフィは悲しい身の上話というより、まるで誰かの手によって書かれた物語を読み聞かせられているような気分で聴いていた。 なぜならユフィはまだ、誰かを心から愛したことはない。 一緒に旅をして色々な物を見聞きし、何かと教える側の立場にあったクラウドが悲痛な慟哭を上げるのを聴き、赤裸々に心の内を語る姿は大きな衝撃だった。 信じられないとは思った。 なんせクラウドと、あの英雄の話なのだ。 だが一方で不思議と嫌悪も違和感も沸かなかった。納得できる気持ちもあった。 そんな風に誰かに執着できることを羨ましいとも思った。 「クラウド、なんか見えるの?」 彼と同じように顔を仰向けて見上げる天井は高い。 穴の向こうは、厚いプレートの合間を縫ってぽっかりと空を覗かせている。 暗い建物の内部へ、その穴から光が帯状になって差し込んでいた。 「すごい、空が見えるよ」 「ここは、エアリスが花を育てていた場所なんだ」 呟くようにクラウドは見上げる姿勢のまま答えた。 「うそ! じゃ、ここの足元に花があったの?」 「ああ」 「ちょっと草は残ってっけど、お花はないねえ」 恐らくここへ逃げ込んだ人々に踏みにじられてしまったのだろう。葉はあっても花は見当たらない。茶色く枯れた残骸があるだけだ。 「クラウド、これからどうすんの? また旅に出んの?」 顔を下ろして頷いた。 元々無口な彼は、昨日から更に無口になった。 「なんならさ、ウータイに来ない? オヤジに頼めば、きっと住むトコくらい世話してくれるよ。なんなら、ウチ間貸ししてもいーしさあ」 クラウドは黙って首を横に振る。 「ダメか。一緒にマテリア育てようって思ったのに〜」 彼の顔にふっと笑みが浮かんだ。 無愛想な彼がそうやって笑うたびに、ユフィは不思議と嬉しい気持ちになる。 いつもそうやって笑っていれば、きっと女の子たちがわらわらと寄ってくるだろうくらい、クラウドは男前だ。そういったことに鈍いユフィでさえ、そう思うのだから絶対だ。 「ユフィは、ウータイに戻るのか?」 「うん。あたしはさ、すんごい強くなったじゃん。ウータイに戻って、腑抜けたウータイの奴らに渇入れてやんないとね」 「うん、強くなったよ、ユフィは」 「でしょー?」 得意げにふんぞり返るユフィに、クラウドは静かな視線を注いでいる。 なんて悲しい顔だろうとユフィは思った。一行でムードメーカーを自称しているユフィをもってしても、もう彼を心から笑わせることは出来ないのだろうか。 勝手気ままに一行に加わり、マイペースを貫いて、それが悲壮な運命を背負う皆の支えになると思ってさえいたのに、それだけ彼の心の傷は重いのだろうか。 「あんたも、たまには顔出してよね。待ってるからさ」 クラウドは頷かなかった。 ただ悲しい微笑を浮かべているだけだ。 そして端正な面をもう一度仰向け、空を見上げる。ユフィもそれに従った。 真っ青な、雲のない空。そこから舞い降りてくるものを見つけ、ユフィは目で追う。 クラウドが腕を伸ばして、その羽毛のようなものをそっと掌に掴んだ。 タンポポの綿毛である。 クラウドの無骨なグローブの掌に、ふうわりと乗るそれは種をつけていた。 「お、どっから飛んできたんだろうねえ。もうちょっとしたら、ここも一面花畑になるかもよ」 クラウドはそっと種を土の剥き出しになった地面に下ろした。ユフィがしゃがみこんでそれに軽く土をかけてやる。 それから見上げると、クラウドはまた天井に仰向いていた。 再び飛んでくる種子を待つように光の帯の中に立っている。明るい黄金の髪が眩く光を纏って、まるで一枚の絵を見ているようだ。 ユフィの胸の奥が得体の知れないものに締め付けられる。 なんだか泣きたいような気分だった。 ここが亡きエアリスの葬送に相応しい緑に埋もれるころには、ユフィを強くしたこの旅が、彼にとっても幸福をもたらすものになっているようにと、祈る気持ちでクラウドと共に丸い空を見上げた。 |
* * * |
| ここ何日か、夜半すぎまで救援作業にいそしんでいた一行は、まだ安らかな眠りの中にある。かつては不夜城と呼ばれたミッドガルも、電気もまともにない今は、陽のない内は動くことも躊躇われる闇に沈んでいる。 夜目の利くナナキは、その獣の体型では皆と同じ作業をすることもできないので、早くに休み、まだ暗いうちに目が醒めた。 拠点の教会の建物は、一行だけでなく寝る場所を失った避難民の宿になっている。あちこちから寝息や鼾が聞こえ、多くの長い祈りに満たされた神々しい風格は失われていた。 ナナキは辺りを見回し、近くにぽっかりと一人分空いたスペースを見つけた。 クラウドがいない。 皆と一緒にそこに横たわっていたはずなのに。残された毛布にはまだ温もりが残っていた。 ナナキは足音を立てないように、しかし早足で屋外へと出た。躊躇わず街の外に向かう通りを走る。 光を失った街灯が、まるで墓標のように静かに立ち並んでいた。かつて繁華街として栄えた八番街は上層から降り注ぐ灰を被って、廃墟のように見えた。 その間を行くと、ミッドガルを囲むモンスター避けのフェンスの近くに、見慣れた後姿を見つけてナナキは足を速めた。 「クラウド…待って、クラウド!」 肩越しに振り返った魔晄の色の目が、ナナキの姿を捉えて細まった。 彼は皆に黙ってここを去る気だったのだ。 ナナキに見咎められて、これ以上にないくらい双眸が沈む。 「なんで、黙っていっちゃうんだよ!」 まるで犬が飼い主に駆け寄るようだと思いながらも、ナナキは体当たりでクラウドに飛びついた。両腕で受け止めたクラウドはナナキを抱えて尻餅をついた。 「ナナキ」 「いやだよ。行かないでよう」 ナナキは太い両足を彼の肩に掛け、獣の性を丸出しにして鳴き声を上げた。 基本的に人間を嫌う種族である自覚はあったが、旅を共にした一行はナナキにとって特別な存在であり、特にクラウドは兄弟のように思っていた。 全てを犠牲にしても志をまっとうしようとする戦士の姿は、ブーゲンハーゲンに諭されたことよりもナナキを大人にした。 だからこそ、これから独り、多くの荷を抱えて長い年月を生きねばならないクラウドの隣にいるのは、ナナキであると思っていた。 「オイラと一緒に行こう、クラウド。オイラならクラウドと一緒にずっと居られる」 だがクラウドは即座に首を横に振った。 「ダメだよ。ナナキはこれからいろんな人に会って、大事な人を見つけて、一族の長になるんだ」 「オイラの一族に加わればいい! クラウドなら誰も文句なんか云わないよ!」 「…お前の一族、か。そうだな、お前といっしょに岩場を駆けるのは楽しそうだ」 「そうだよ!」 クラウドの胸から顔を上げ、ナナキは彼の顔を見た。 だがそれは酷く辛そうに歪んでいた。 まるで笑うことにしくじったような、そんな表情だった。 「駄目だよ。…駄目なんだ」 歪めた顔をナナキの首筋に埋め、クラウドは声を詰まらせ、嗚咽を漏らした。 ナナキは身体を強張らせ、息を飲んだ。 「オレを満たせるのは、あの人だけなんだ」 「…セフィロス…?」 「うん。…オレはずっとそれから目を背けてきた。あの人を倒さなけりゃならなかったから。あの人を止められるのは、オレだけだったから。オレは以前それを怖がってやらなかった。だからやった。でも…」 顔を少し離して、クラウドの手がナナキの背を撫でる。 彼は時折そうしてくれた。まるで母に毛づくろいされるような、慈しみと一緒に。 小さく鼻が鳴った。 「でも、今でも忘れられないんだ。あの人がいなくなって、オレは、半分だけになった」 「半分…?」 「身体も、気持ちも、全部が。だからお前と走っていても、きっとオレは半分だけしか楽しめない」 恐ろしい告白をされながらも、ナナキはそれに頷かざるをえない気持ちになった。 そう言って浮かべたクラウドの笑みは確かに以前と違っていた。セフィロスを憎み、その気持ちだけで北の大空洞に向かっていた時の方が、よほど満たされていたのだろうとナナキにも分かるくらいに。 「皆にも黙って行くの?」 「…お前みたいに、止めるだろ? 断るのは辛いから」 クラウドは立ち上がり、もう一度手を伸ばしてナナキの頭を撫でた。 「幸せに。一族を率いるに相応しい長になれよ」 整った造作の顔が近づき、耳の間の額に唇が触れた。 「立派な長になったら、会いに来てくれる?」 「…約束するよ」 細く開けた門扉を通り、クラウドはミッドガルの外へ出て行った。 隔てるフェンスが、まるでナナキと彼の間にある距離を倍にしているような気にさせる。ナナキは門まで走り寄って座り、追うことを拒絶するその背に吼えた。 遠く、どこまでも聞こえるように。 決して仲間たちは彼を忘れないと伝わるように。 荒れた土地にはろくな草も生えず、一面土の地面を晒している。そこを南へと独り進む彼の後ろ姿はいつまでもナナキの視界から消えなかった。 ここに青く草花が芽吹く頃、ナナキは一族の長として生き、彼もまた長い人生の途中かもしれない。 クラウドがその持て余すほどの年月を生きる内に、いつかナナキが彼を助けるべき時がくることもあるだろう。 その時まで。 クラウドの背が見えなくなってから、ナナキは光る尾を振ってきびすを返し、仲間の待つ町に戻っていった。 いつしか東の空から眩い朝日が昇り始めていた。 |
* * * |
クラウドという青年は、時折俯き加減で目を半分伏せ、憂いのある表情をする。 その彼に自分と似た境遇を見出していたのは、ヴィンセント自身だけではなく、周囲もそうだったようだ。 実際、愛する者が人としての道を違えていくのを黙って見ていることしか出来なかった己に、クラウドは多大な罪悪を感じていた。ヴィンセントは同じ後悔を持つ者であることも、彼とセフィロスとの関係も、クラウドの口から語られる以前からある程度察していた。 そんな彼が酷く愛しいのは、同胞愛なのだろうと思う。同情を拒む気持ちも、救えるのはただ一人のみと分かっていても、だからこそ見捨てては置けなかった。 メテオが消滅して一週間も経たない内に、クラウドはミッドガルに仲間を残して消えた。 セフィロスを捜しに行ったのだとヴィンセントは思った。 彼は諦めていない。 全てを失った落胆の中にこそ光を見出す男だ。 クラウドはただ過去を悔やむだけでなく、そうやって自ら何かを掴み取ろうとする。自分の弱さを認知し、受け入れているからこそ、強く逞しくあろうとする。 彼と共に歩いた旅路で思い知ったことだ。 ヴィンセントはルクレッツィアに再会しても、思いを伝えることもろくに出来なかったの言うのに。彼の姿に、そうやっていつも己の弱さを突きつけられるのだ。 「ルクレッツィアの元に行ってこようと思う」 意を決したヴィンセントがそう仲間へ口にしたのは、クラウドが消えてから二日後のことだった。 飛空挺でジュノンまで送ってもらい、ヴィンセントはそこから独り、神羅から奪った潜水艦を使って海底を進んだ。深い海溝に口をあけた空洞をくぐると、西大陸の中央にある湖に繋がり、それに注ぎ込む滝の裏にある岩の祠に、ルクレッツィアは居る。 以前に二度ほど訪れたが、最初に会った時以来彼女は姿を見せていない。 ヴィンセントと同じく自分の犯した罪の重さにずっと打ちひしがれていた彼女は、恐らくその変わらない美しさを保ったまま、ここで生き続ける覚悟なのだろうと思った。 彼女の気持ちが分かるからこそ、静かに見守ることがヴィンセントに出来る唯一だったはずだ。だが、今ヴィンセントは違う目的の為に再びこの祠を訪れていた。 「ルクレッツィア! 出て来てくれ」 反響する狭い祠の奥、外側からは開くことのできない岩戸の向こうの彼女に聞こえるよう、ヴィンセントは大声を張り上げた。 「話がある。出てきてくれ!」 何度そうやって声を掛けたのか、暫くすると重い音がして岩戸が動いた。 「ルクレッツィア!」 「ヴィンセント…なぜ来たの」 「聞いてほしいことがある」 祠の奥から現れた彼女は以前よりもやせ細り、幽鬼さながらの姿だった。 「君の息子…セフィロスのことだ」 「…セフィロス…」 ルクレッツィアは弱々しい足取りで歩み寄り、差し出した腕に縋った。細い骨ばった手首にの感触に背筋を冷たくしながら、ヴィンセントは彼女を石段に座らせ、髪を撫でた。 「美しいルクレッツィア。オレや君が罪を贖う時が来た」 「罪…」 「力を借りたい。私が眠りから目覚めたように、君ももうここに居るべきではない。君の息子を救うためにも」 「私の…セフィロスを…? あの子は死んだのではなかったのね」 ルクレッツィアはヴィンセントを見上げる目を大きく見開き、乾いた唇を僅かに震わせた。 「わからないんだ。だが救えるかもしれない。それに、セフィロスが愛し、彼を愛した青年を救うために」 見開かれた瞳から大粒の涙が零れ落ちた。 悲哀に強張った無表情よりも、ずっと美しい顔だった。 だが同時にヴィンセントは気付いた。 大事な人だが、長い年月で恋心は殆どその形状を失っている。彼女に感じるこれは、クラウドにも感じたような同胞愛だった。だからこそ、まだ前途ある青年の為に、自分たちが何かしてやれることがあるはずだ。 「だから私と一緒に考えてほしい」 ジュノンへ帰港する潜水艦の狭いブリッジに毛布を敷き、やつれたルクレッツィアの身体を横たえた。 だが彼女の顔は、これまでになく生気に満ちているようにも見える。 青年の決意に突き動かされたのは、今やヴィンセントだけではない。 「ヴィンセント…セフィロスが愛した人の名は、何というの?」 「クラウドだ。クラウド・ストライフ」 「クラウド」 青年の名を復唱して、ルクレッツィアは酷く嬉しそうに笑った。 「どんな人?」 「あの祠に一度一緒に訪れたんだが…覚えてないか」 ルクレッツィアは少し考え、それから首を横に振った。 「そうだな…」 ヴィンセントは操縦桿を握ったまま、目を細めて青年の姿を思い浮かべた。 「強く、美しい青年だ。あなたの息子と同じくらいに」 彼の名が意味する『雲』の隙間を差す陽光のように、人々に希望を与える青年だと。 だからこそセフィロスが愛したのだろうと。 長い長い話をヴィンセントは語りだした。 |
* * * |
クラウドは自分の手で育てた海チョコボの背に乗り、遠く北の果てに臨む山の大空洞を目指していた。 一直線に空を行く飛空挺とは違い、多少時間はかかる。野営を繰り返し、チョコボファームからそこへ辿り着くまで約五日の行程だった。 クラウドはセフィロスの最後の日以来、眠りに着くと夢を見る。 彼が呼んでいる。 大空洞での、二人きりの対決の時のようにクラウドの名を愛しげに囁き、もう一度戦えと、最後の最後で彼に剣を振るうことを躊躇したクラウドを責めている。 二人は共に、五年前から互いに互いを裏切り続けたのだ。 セフィロスは我を忘れてクラウドの大事な人間を二人も殺め、クラウド自身も捨てた。 クラウドは真実を忘れ、セフィロスを宿敵とあだ討ちに走った。二度目に彼へ剣を向けた時、決着を恐れたこともまた、裏切りであると言えるだろう。 それだけ互いを憎みあっていたはずなのに、セフィロスを失えばクラウドはまるで空っぽの自分に気付く。 そんな自分は知りたくなかった。 辛く長い旅を終えて、漸く心安らかになれると思っていたのに、この半身の肉を失ったような気分はなんだろうか。生きながら切り裂かれ、切断面から徐々に血液や感情をす失っていくような、この痛みはなんだろうか。 消えろと強く願っても、クラウドの中の彼の存在は、残された半身にしっかりと留まっている。 男の端正な顔、大きく美しい手、鋼のような髪、厚い胸、見惚れるような長い足。 煙草を吸う仕草、クラウドを抱く時の意地悪い笑み、敵を前にした鋭い視線も、熱い吐息も全てが鮮明で。幸せだった日々を捨て去るには、それは余りに短く印象深い出来事ばかりだった。 あの日々を取り戻す為なら、今のクラウドはきっと、一度は救ったこの星さえも破壊してみせるだろう。 彼を取り戻すためならば。 大空洞は数日前とはその姿を大きく変えていた。 セフィロスが倒れ、白マテリアから発動されたホーリーの威力は凄まじく、周囲の岩盤を砕き、地底から溶岩を噴き出させ、まるで穴を塞ぐように岩の床が出来ている。火口の縁からその床までは二百メートルはあろうか。断崖をロープなどで降りるのは非常に難しい絶壁で、クラウドは海チョコボでここまで来たことを幸いに思った。 山肌も登るチョコボの足は逞しい。 僅かな岩の突起に足を掛け、時間はかかっても確実に火口を降りていく。 そして降り立った床状の岩面は、まだ完全には冷め切っていないようで暖かかったが、触れられないほどではなく、表面も固い。所々裂け目があり、遥か下にあるライフストリームの緑色の光を漏れさせている。裂け目はなんとかクラウドが通れるくらいのものだった。 クラウドはチョコボのハーネスを外してやると、優しく言い聞かせた。 「ベアトリクス、お前は自由だ。森で暮らしても、チョコボ仙人の家に行ってもいい」 首筋を撫でてやれば、生まれた時からクラウドに懐いているメスのチョコボは、優美な形のくちばしでクラウドの髪をくすぐる。そして寂しげに一声鳴いた。 「いつ戻ってこれるかわからないんだ。お前をここで待たせる訳にはいかない」 背を軽く叩いて促すと、彼女は渋々といった様子でクラウドから離れて行った。時折クラウドを振り返り未練を見せたが、見送る主人の命には逆らえず、元来た断崖を登り始めた。 そしてクラウドは剣を抜き、その刃を見つめた。 仲間と別れる際、クラウドは自分の剣と僅かな装備しか持ってこなかった。マテリアも成長途中のごく一部だけ。持って来ても、ここでクラウドの身体と一緒に朽ちるだけなら、マテリア好きのユフィに残した方がよっぽどましだろうと思ったからだ。 この期に及んで懐かしさすら覚える仲間の反応を思い出して、クラウドは苦笑した。 ティファを泣かせてしまっただろうか。 しかしもうクラウドが居なくても、彼女は誰よりも強く生きていける。それに気付きさえすれば。 バレットはカームに避難していたマリンと共に、幸せな家庭を築き直すことができるだろう。迷いのない彼はとても行動的だ。 ナナキは一族の元に戻るだろう。立派な長になったら会いに行くと約束してしまったが、果たせなかったら怒るかもしれない。 シドはきっと今度こそシェラとうまくいくだろうと思う。 旅をして、彼はとても優しくなった。そして二人で空へ馳せる夢を育てて行くことだろう。 ユフィはウータイに戻ると云っていた。マテリアのことで、また皆と喧嘩していなければいいのだけれど。 ケット・シーもといリーブは、多分神羅が崩壊して乱れたミッドガルや周辺の町を復興させるための要となるだろう。何も協力しないまま逃げ出してすまないと思う。 ヴィンセントは遂に思い切れなかったルクレッツィアの元に行ったかもしれない。それともまたあの暗い屋敷の地下に戻る気なのだろうか。 逃げるように抜け出して来ても、皆を大事に思う気持ちは変わらない。 思い出すほどに温かく優しい記憶だった。彼らと共に過ごした日々は確かに幸せだった。 だがこの岩盤より下に向かったら、クラウドはもう彼らを慮ることは出来なくなるだろうと思う。 幸せで楽しい日々の記憶を、あの男は自分としか持てなかったと知っているから。 彼にとってはクラウド一人しかいないのだから。 クラウドにとって一番幸せな記憶が、彼とのものであるように。 「どうか元気で。みんな」 火口に丸く仕切られた曇り空を仰ぎ、祈る。 未練を振り切り顔を戻すと、クラウドは岩の裂け目に身を滑り込ませた。 戦いは別離を生むものだと誰かが言っていた。 だが、別れこそが己自身との戦いだということを、彼らはこの大きな戦乱の最後に知ったに違いない。 |
| 賛美歌146番「戦い終わりて〜The Strife Is Over, the Battle Done」より抜粋 |
| 最後の日(了) 03.08.10 アイコ<http://www.natriumlamp.com/B1F/> |
| NatriumlampB1F since 2003◆All rights reserved. |