| 1 |
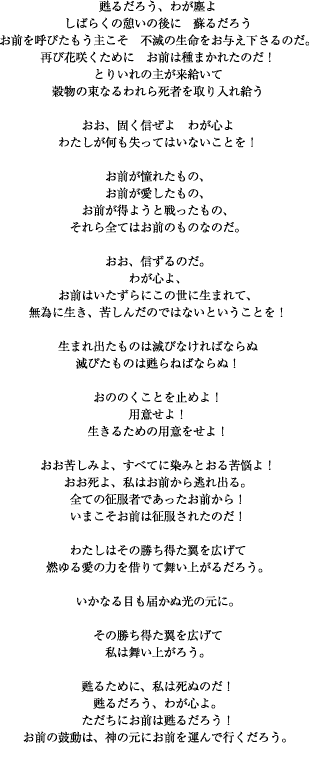 |
|
よみがえ わが ちり |
自分の骸が見えるという不可思議を、男はもう幾度経験しているか知れない。 朽ちた様子はないが、抉れた肉や所々骨まで見えているそれが、岩場に打ち捨てられている有様は間違いなく死体だった。 だがそれを視認出来るということは、やはりまだ肉体は星に帰ってはいないということだ。 かといって、どんなに男が精神を集中しようとも、己の意思でその躯を動かすことは叶わなかった。指先の一本も、瞼を上げることも、無論声を発することも出来ない。凍りつき、時間を止めた躯の周囲に、確実に時間は流れているというのに。 既に死体と同意のそれを放置して、この意識だけでも星に帰ることができるのかもしれないと思い至った。この世界に存在するもの全てに拒まれ続けてきた男を、生命の流れが受け入れてくれれば、もうなんの柵も存在せず、心安らかに死の国へ旅立てるはずだった。 伝説にあるように、死した戦士を迎える美しいバルキューレは現れないが、それでも大いなる母は確かに居た。信じたことも、崇めたこともない『神』といわれるものは、まさしくあれだろう、狂気に駆られた己へ否応なしにも知識を与え、我が子を悲哀と慈愛に満ちた目で見つめ、彗星を呼んだ行為に嘆き悲しんだ。 今この惑星上にはその気配が満ちている。 一方、男を産んだ呪われし母なる存在は、既に意識の欠片も感じなくなっている。 この身体と数人の人間にその遺伝子を植付け、母親としての使命を終えたのだ。 それにとどめを刺したのが、子にあたる一人であることに、彼女は僅かでも悲しみを感じたのだろうか。 いや、あの巨大な化け物と呼ぶに相応しい、本能のみで動く存在が悲しみなど感じるはずもない。彼女の息子である男が、それを感じないように。 一瞬だけ男へもヒトらしい感情を与えたあの青年は、今何処で何をしているだろう。 時折、骸に縛りつけられ動くこともできない精神が、あの青年の声を聞く。 耳はないそれがどうやって声を聞いているのか、確かに、聞き覚えのある声が諦めと悲しみに満ちた感情をぶつけてくる。 己を恋しいと嘆く。 『オレも、会いたい』 そう素直に答えるのはきっと己のヒトの部分なのだろう。 呪われた細胞もヒトの感情を識ってはいるが、既に意識は離れ、そこにはないのだから、これは紛れもなく己の意思であるはずだ。。 囁きかける青年の声に返答すれば、波のように寄せてくる青年の意識は和らぎ、微笑む。 『愛しいオレの半身』 傍に行きたい。 その微笑を映像として目に焼き付けたい、もう一度。 かつては自身を狂わせた強烈な恋慕が、いつこんな風に慈しみにも似たものに昇華したのか。いつから、ただ青年を慰め、心落ち着かせ、安らがせたいと思うようになったのか。 しかしそんな執着があるから、きっと男の精神は星に帰ることさえできない。 腐らずにある肉体に戻ることができれば、青年の元へ行けるだろうに、それも出来ない。 『なんとかしろ』 母なる存在はそこにあるのに答えない。 『動け!』 躯に叱咤したところで、やはりそれはぴくりとも動かなかった。 青年の声を何千回目に聞いた時か、セフィロスは意識にある『目』を開き、彼の姿を探した。 記憶にあるより成長した姿が見えた。 懐かしさと、湧き上がった喜びに『口元』は自然と緩んだ。 剣を握るに相応しい身体になった。腕は己のものとそう変わらない逞しさ、腰が割れ、安定感がある立ち姿である。余り変化がないのは滑らかな頬、少し細くなったが幼さがまだ残っている。首と腰は男の形をしているのに細い。セフィロスの両手で握り取れてしまいそうだった。 「クラウド」 斜に構えて上目遣いに睨みつける気の強さも変わらず、セフィロスは躊躇いなくそこに『手』を伸ばした。 己の視界に、あるはずのない自分の手があった。 これは夢か幻影なのか。 『触るな。オレがあんたを許すと思うのか』 ふとよぎった少女の面影にセフィロスは眉を寄せる。 己の意思で操ったコピーの手で、命を奪わせた少女のことを言っている。 クラウドはあの娘を深く愛していた。 「許さずともいい」 『オレの悲しみがあんたに分かるか』 「だが今お前が呼んだのはオレだ。あの娘を呼んではいない」 幻影のはずの青年の頬は、朱を刷き、唇を噛んで一層強く睨みつけてきた。 それも堪らなく愛おしい顔だった。 『でもあんたは呼んでも来ない』 「オレは、ここから動けない」 『来ないじゃないか。こんなに呼んでも』 「クラウド」 『あんたは来ない』 泣き崩れそうな顔を俯けて。 なぜ成長しても、彼はこれほど小さく見えるのだろう。 「お前の元へ行く方法があるのなら」 肩に手を乗せようとして、それがいつしか少女の物になっていることにセフィロスは気付いた。 茶の緩い巻き毛は長く、後ろでひとつにくくっている。少女らしいリボンが嘆くたびに揺れる。 『なぜひとりにしたの』 うめくように発された声に、セフィロスは伸べかけた手を退いた。 『なぜ彼をひとりにしたの』 少女は顔をあげ、涙に濡れた頬を拭いながらセフィロスへ詰め寄った。 『あなたはまた世界を滅ぼすつもりなの』 「いいがかりを」 『いいがかりじゃない。あなたは、彼と離れては、いけなかった。このままじゃ彼は』 必死の形相は幼さすら残すのに、セフィロスに微かな恐怖を与えた。 セフィロス自身がかつてその意思で殺めた少女であるが、生身の頃、その手で息の根を止めた生き物など数え切れないほどだ。それを恐ろしいなどと改めて感じたことはない。 だが無垢なものは、いつもセフィロスを躊躇させる。 かつて、あの青年がそうだったように。 『クラウドを、助けて』 「頼まれずとも、できるならやっている」 『あなたも彼も、このままでは何処にも行けない。この星も迷っている』 少女は突然大人びた顔つきになり、深い緑の瞳を細め、セフィロスを見下ろした。 セフィロスよりずっと小柄な少女が、どうして自分を見下ろすことが出来るのだろう。 疑問に思う内に、少女は細い右の指を挙げ、一点を示す。 『導きが必要なら、己の胸に聞けばいい。己の右半分の身が、神だということを忘れたのか』 「神…だと?」 セフィロスは少女の顔をしたそれを見つめ、鼻で笑った。 「己の欲しい唯一のものすら手に入れられなかったオレの、どこが神だ」 表情を無くした少女に変化はないが、深い眼差しがセフィロスを探るように見ている。 『お前は既に、その唯一をその手にしていることに気付いていないだけだ』 「オレの手にあると?」 セフィロスは手を持ち上げ、己のそれを見下ろした。 見慣れたグローブの手に何があるのか。 ふと、右の掌に光のようなものを見た。まるで蛍が命の終わりに明滅するように、頼りない僅かな光である。光はよろよろと輝きながら移動し、セフィロスの前方へ飛び立った。 思わず『足』を踏み出し、その光点を追いかけた。見失ってはいけないと知っていたからだ。 『追って、その手にあることを確めるがいい』 少女だったものの声はそれきり途絶えた。 セフィロスは無心に小さな光を追いかける。 『まばたき』も忘れ、足元を見ることもなく、だが近くに寄って『腕』を伸ばしても、その手に掴むことは出来ない。 「オレを試しているのか」 際限のない追いかけ合いを繰り返しているようで、とても正気の沙汰ではないように思える。一度はこの掌にあった光であるのに…。 ふと、セフィロスは足を止め、もう一度右手を開いて覗き込んだ。 光がある。そこに。 小さく明滅する、まったく同じものが。 変わらず傍にあり続けた、懐かしいものが。 「クラウド」 少女の顔をした、あの奇妙な存在が言っていた。 欲しかったものは既にこの手にある、と。 「クラウド」 光を握り締め『膝』を折り、あるともつかない地面にそれをついて、その手を『胸』に押し当てた。 自分の『鼓動』に、光の明滅に合わせた別の鼓動が重なり、セフィロスの『耳』を打った。 「やはりオレの半分をお前が、お前の半分はオレが持っていたのか」 セフィロスは目を開き、立ち上がった。 「それを奪い合い続けるのがオレたちの運命か。それとも」 握っていた手を開き、光点を中空に解放つ。 「互いを、いっそ他人にくれてやれということか」 上へと舞い上がった光が突然大きくなり、セフィロスの視界は真っ白に染まった。 水中から引き上げられる感触に似ている。水面が近いことを何故かセフィロスは知っている。 手を伸ばせば、求めているものに今こそ辿り着けるだろう。 指を光へ差し伸べた。 二度目の生を得られるのなら今度こそ唯一求めた者だけの為に。 そうすればこれまでの苦悩も、犯した罪も、無駄ではないと思えるに違いない。 瞼が微かに痙攣し、指先が地面を掻いた。 |
* * * |
| お前が憧れたもの、 お前が愛したもの、 お前が得ようと戦ったもの、 それら全てはお前のものなのだ。 |
| 03.10.10(了) アイコ<http://www.natriumlamp.com/B1F/> |
| 注釈 マーラーの代表作である交響曲第2番「復活」第5楽章の最後に、壮大なオーケストラと合唱・ソプラノ独唱・アルト独唱によって力強く歌われる「よみがるだろう、わがちりよ」は、マーラーが感銘を受けたという、クロップシュツックの詩を用い、マーラーのオリジナルの一節(「その勝ち得た翼を広げて〜」の末尾部分)を加えたもの。 管理人は十年くらい前からクラシックを聴いているが、それほどマニアではないため、マーラーの初級編ということで、サイトウキネン・オーケストラ(小沢征爾指揮)によるアルバムを主に聞いている。 訳詞は翻訳家によってかなり異なるので、今回は最も好きな渡辺護氏によるものを引用させていただいた。 |
| NatriumlampB1F since 2003◆All rights reserved. |